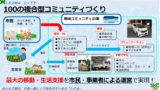大阪ガス都市魅力室の山納洋さんが主催されているTalkin’Aboutに参加してきました。話題提供者は大東公民連携まちづくり事業株式会社代表の入江智子さんです。
Talkin’Aboutとは?
“Talkin’About”は、あるテーマについて興味・関心を持った人たちが集い語り合うサロンです。思いある人たちが自由に集い、情報を交換し、ネットワークを広げ、そこから自然なかたちで新しいアイデアやコラボレーションが生まれていく、そうした場づくりを目指しています。
話題提供者は大東公民連携まちづくり事業株式会社代表の入江智子さん
今回の趣旨は
近年、行政と民間事業者が協働で公共サービスの提供などを行う「公民連携=PPP(Public Private Partnership)」が注目を集めています。行政が民間セクターと連携し、アイデアや技術、ノウハウを取り入れることで、市民サービスの向上や事業効率のアップ、地域活動の活性化、新たなビジネスを創出させることをその目的としています。
大阪府大東市では、市民の笑顔が集まる個性的な街をめざし、2016年に大東公民連携まちづくり事業株式会社(コーミン)が発足。これまでにJR住道駅前での「ズンチャッチャ夜市」、「地域健康プロフェッショナルスクール」の運営、地域包括支援センターの運営受託などを行い、今年3月には「morinekiプロジェクト」として、PPP手法を用いて整備した借上げ公営住宅・民間賃貸住宅の住宅棟、生活利便施設をオープンさせます。
今回は、「コーミン」の代表取締役の入江さんに、活動の趣旨と大東市でのこれまでの取り組みについてご紹介いただき、「地域における公共サービスを、ビジネスの手法でどう解決するか」をテーマに話し合います。
以下、狩野のオボロげな備忘録です。いつも以上にめちゃくちゃあやふやなメモです。ご了承ください。
入江智子さんの会社と会社でやっているプロジェクト
・3/19グランドオープン
・2016年秋に着手。それまで大東市の職員→退職して民間人に。市が出資してできた会社。
プロジェクトの舞台は大東市
・人口12万人、製造業、倉庫、物流業が中心、住道が中心地、3分の1が山間部。四條畷駅は四条畷市ではなく大東市。
・もともと駅前に市営飯盛園第二住宅という団地が建っていた→老朽化→解体完了。
→ベランダに風呂をつくったり、子ども部屋をつくっていた。
morinekiプロジェクト
「morinekiプロジェクト」は「北条まちづくりプロジェクト」のスタートアップ 事業として、市営飯盛園第二住宅の跡地に、全国で初めてPPP手法を用いて、借上げ公営住宅・民間賃貸住宅の住宅棟、生活利便施設等の整備を行うものです。
・平家のレストラン、商業施設も。木造。RCは高い。20年の間で勝負しないといけない。減価償却の短い木造は有利。
・背景 地元民は建て替えてくれと市役所に言っていた。住みたい人を増やしてほしい。イメージを一新するようなまちをつくろう。
→144戸から74戸に。団地のエリア全体に住みたい人をつくる。オフィスもある。民間企業が丸ごと借りてくれた。
→権現川に降りる親水護岸も考えている。
・公民連携だからできたすごい形。
→基本設計を委託してもらえたからできた。
→設計などは入札でやった。
・高齢化で一人暮らしが多かったから1LDKが多い。
→見守りの意図も
丸ごと借りてくれた民間企業は2社
north object本社移転
アウトドアショップ「ソトアソ」

物件とまちの未来像
・ターゲット層はすっぴん女子と名付けている→心がすっぴんな人。男性も含めて。
雇用が生まれている
・north objectで働く人が増えている。このエリアに住みたい人を増やす。マーケットに認められる場所にしたい。
物件の分析
(以下、意味がわからずメモしてます。あとで時間があれば調べよう。)
PPPエージェント
大家 東心株式会社
運営 コーミン
・銀行からプロジェクトファイナンスという借方をしている。無担保無保証でお金を借りる。専用のお財布会社=東心が必要。社長は市営住宅の住人さんになってもらった。プロジェクトの信用性で借りている。
・テナントさんと15年契約
・市役所とも20年契約
・土地は市役所のまま。土地代1000万円払っている。
・家賃は所得に応じて払ってもらっている。
・管理もコーミンが行なっている。
・オリンピックの効果で資材費がブワッとあがってしまった。
借り上げ住宅に賛否両論ある
(ここは知識がなさすぎて話についていけなかった)
公共サービス
入江さんの師匠の師匠の言葉
本当に求められるのは
・公共サービスの質を高め
・経費を削減し
・加えて税収を増やすことではないでしょうか?
→自治体経営の視点で必要、あきらめずに進めてきた。
・過去 標準的な市民ニーズにあわせた行政サービスを提供
・現在未来 多様化する市民ニーズに対しそれぞれを満足させる公共サービスを提供
→それぞれのニーズにブスッと刺さるやり方
→それをするには公民連携が必要だと思っている
組織がもつ動機をリンクさせる
自治体
地域事業者
地域金融機関
金融機関のおそれはテナントに逃げられること。テナント企業さんがやりたいことをいっぱい応援していこう。
大東ズンチャッチャ夜市
・死にそうな砂漠のようなデッキJR住道駅前。もともとバスロータリーとしてつくられた。商店街の反対でバスは地上を走っている。
・出店者は一軒ずつおいしいと思ったものを出してもらっている。
→お店の見せ方、ドレスコード。
→ここでもマーケット。
→適性なもの。
→地元のお店さんが新規顧客を開拓することを目標にしている。値段は絶対下げないでください。水曜日の夜にしているのも週末に稼いでもらうために。
雑誌「Nukui」
飾らず自然体な女性「すっぴん女子」と創る、大東ライフを10倍楽しむためのWebマガジン「Nukui」という情報誌をつくっている。
?
毎週や毎月行うことの最大のメリット
マイナーチェンジしかできない
コーミンは「まちづくり会社」
大東市基幹型地域包括支援センター
→委託を受けてやっている。2019年4月スタート。地域包括ケア。住まいには居場所が必要。家から出て、行きたいと思える居場所が必要。孤独な人をつくらず、活動的な生活をあきらめている人の背中を押すような事業をいろいろとやろう!
カフェ1軒つくるより、ゴミ屋敷を1軒減らすほうが大事ではないか。
会場からの質問で気になったところをメモ
オガールプロジェクト(岩手県・紫波町)
修行に行って開発手法を学んでいた。
morinekiのおしゃれなお店は住民の居場所になる?
近大・高橋先生の質問。もともと市営住宅だった。ここにあるお店は住まれている人には居場所にはならないのでは?
→住民さんたちは駅前で買い物できる。
→パン屋ができる。めちゃくちゃ楽しみにしてくれている。地域の方に開放する社員食堂も。
→来訪者がよくきてくれる場所になりたい。
真の公民連携はあるのか?
あると思いたい。公のほうが意思決定が遅かったりするのは当然。民はぐいぐいいく。これまでにこれをしてくれないとできませんよと言えば真剣についてくる。なにより政治をまとめてくれることに期待。公民政治連携という感じ。ここが一番大事なところかな。
夜市、すごい調整が必要なのでは?
実はあんまり交渉していない。商店街とか商店会にはいっさい言わずにはじめた。そのかわり募集は広く開いた。ただ、落選する。企画メンバーが何人かいて。力のある人の息のかかったアレがエントリーしても落選する。市場をつくる。
→こっちがお願いするとダメ。マーケットをちゃんとつくれば文句はでない。
→実店舗をもっているか、これから持とうとしている人。しっかりこっちの軸があればあんまり調整いらない気がする。
そもそもの原体験は?
大東市職員。建築職。ちゃんとした大家さんになりたかった。入札でしか決めれない。建築士泣かせ。公営住宅にいろんな疑問をもっていたのもある。
まとめ
今回はコワーキングスペースのおしゃべりNGの集中ルームにいたので質問しませんでしたが、気になることはすべてみなさんの質問でクリアになりました。詳しくないPPPの分野は聞いても頭に入ってこなかったので少し調べてからお話を聞けばよかったです。グランドオープン後に行ってみたいと思いました。
拙著とグループページの宣伝
拙著「まちのファンをつくる 自治体ウェブ発信テキスト」学芸出版社を書きました。ぜひ読んでみてください!

また、拙著と関連した公開のグループページをFacebook上につくっています。まちの情報発信のアイデア集的なコミュニティを目指しています。どなたでも参加可能です。お気軽にご活用ください!
拙著「#まちのファンをつくる 自治体ウェブ発信テキスト」(学芸出版社)と関連した公開のグループページをFacebook上につくっています。あと一人で50人に! まちの情報発信のアイデア集的なコミュニティを目指しています。どなたでも参加可能です。お気軽にご活用ください!https://t.co/zYkPj2T0ou pic.twitter.com/85Vh4XKE7K
— 書籍「まちのファンをつくる 自治体ウェブ発信テキスト」(学芸出版社)公式アカウント (@kanolaboratory) February 15, 2021
Talkin’Aboutバックナンバー